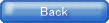
| ノーマライゼーション・教育ネットワーク 会員通信 2023年秋号 ~2023年9月21日発行~ 【事務局】宮城道雄 〔ホームページ〕 URL:http://www.japan-normalizatio.com/ 連絡先〈 郵便 〉〒344-0041 埼玉県春日部市増富763-1 飯島気付 〈 電話 〉090―5994―5131(宮城) 〈メール〉rsj78162@nifty.com(宮城) 新井淑則代表の葬儀に参加して 宮城道雄 新井代表は、昨年3月に定年退職しました。その後、体調が悪く、通院して、肺がんと難病と診断され、治療困難な難病と分かり、闘病生活を続けていました。去る7月5日に寝たきり状態のまま急に亡くなられました。残念なことです。 新井淑則教育ネット代表の葬儀は7月8日午後2時から皆野町のメモリアルホール皆野において行われました。前夜の通夜は卒業生などが来ていたそうですが、葬儀は広い会場にいっぱいの方々が参列しており満席でした。会場前は沢山の花輪が飾り付けられ各方面とのつながりを感じます。会場に入ると新井先生が教室で琵琶を奏でている写真と思い出の品などが飾られ厳粛な感じでした。 教育ネットでは事務局員飯島、岩井、宮城の3名が参加。森谷は香典のみ参加でした。お坊さんがお経を唱える中で焼香がしめやかに行われました。 その後に追悼の辞が行われ、横瀬中学校時代の同僚からの新井さんの人柄を思わせる言葉や、卒業生代表の2人の方の声を詰まらせた涙ながらの追悼の深い思いが語られました。教師として慕われ尊敬されていた新井先生の姿を想起させる言葉でした。 そして喪主の長男の方から謝辞があり、また家族代表の新井さんのお姉さまにあたる方から、言葉があり、新井先生の情熱的に教師として活動してきた事柄や、宮沢賢治の雨にも負けずを毎日唱えながら病気と闘っていたなどのお話がありました。全盲になっても障害者として復職し、中学校教師として生徒に慕われ、生き生きとした教育活動をしていたのだと感動させるほどでした。 その後、弔電が披露され,沢山ありましたが,NHKのディレクターやJVTからの弔電も披露されていました。 会場で新井さんの親しい友人の高橋さんに会い、会場の写真を取ったものを後程メールで送っていただきました。また、帰りは皆野駅まで車で送ってもらいました。新井さんと一緒にリルの家をやろうと計画していた方です。新井さんの思いを大切にしてリルの家実現に向けて取り組んでいるそうです。 新井淑則先生の追悼文集、原稿募集について 今回教育ネットでは長年教育ネット代表を努めてきた新井先生をしのんで、追悼文集を作ることに決めました。つきましては多くの皆様に新井先生に関する追悼文を書いていただける方を募集します。原稿はA4用紙3枚以内でお願いします。1ページ40文字40行で10,5ポイントでお願いします。原稿締め切りは本年10月末日までです。電子データを添付して事務局の宮城まで送信して下さるようお願いします。 総会報告 飯島光治 2023年7月29日、1時よりの予定が、遅れて始まりました。 最初に新井淑則代表の冥福を祈り、黙とうをしました。 参加者は、13名で会員8名(オンライン参加2名含)、学生2名、ヘルパー1名、講師と付き添いの方2名。 議長は岡安さん、各号議案は、学生さんが朗読しました。 第一号議案 2022年度活動報告。 2022年度活動総括 第二号議案 2022年度決算 第三号議案 2023年度活動方針 第四号議案 2023年度予算 第一から第四号議案まで、各号ごとに採決しましたが、質問、意見が無く拍手で承認されました。 尚今回、集合待ち合わせに問題があり、人数確認が不十分なままに、駅の誘導係(2名)が、12時半のバスに乗ってしまった、が反省点となりました。 また、会員の方には、議案書とイベントの資料を7月31日に郵送しました。 教育ネット第28回定期総会の振り返り 岡安 秀展 教育ネット第28回定期総会が令和5年7月29日土曜日に埼玉県障害者交流センターで開催された。当日は気温35度を超える猛暑日だった。 都内の線路付近火災による影響のため、13時からの開催時刻は大幅に遅れた。 参加者は13名、内訳は会員8名(オンライン2名)、ヘルパー1名、学生2名、講師と付き添いであった。 開会式ののち、自己紹介を兼ねた挨拶が交わされた。 第一部定期総会の終了後、10分休憩して第二部ではN先生問題とその復職を考えた。 ここでは、N先生が休職に追い込まれた経緯と問題の理解・把握及びそれを解決させるための手立てを考えた。 まず初めにN先生から現在までの状況の報告と訴えをお聞きした。次に、事務局から問題の内容と経過報告 、事務局によるある程度の方向性を提起された。 東京都教委の障害者活躍推進計画の概容とその活用の報告がなされた。 今後、教育ネットはN先生と連携しN先生問題に関して教育委員会と交渉する予定だ。 休憩をはさみ、さいたま市心の健康センターの講師、曲渕 祥子先生による講話(「鬱の実際と社会の現状」)を拝聴した。講師の曲渕先生は精神保健福祉士であり私は精神保健福祉士という国家資格があることを初めて知った。 鬱や精神障害など心に病を抱えた方が、スムーズに社会参加や社会復帰できるように相談、生活支援、助言される頼りになる方が社会福祉士以外にも存在することを学んだ。 私は一昨年度より復職し、今年度は異動した勤務地で二年目を迎えた。 通勤方法は昨年度とほぼ同様、電車とバスを利用している。 朝のバスが1本減便され、電車遅延の際にはやむを得ずタクシーを利用する機会が増えた。 退勤時は信号機のない横断歩道を渡る。 昨年度までは補助をされていた先生の協力を得られていたが、今年度はその先生が退職され、新たな補助の先生は配置されず、困惑した。 現状は親切な先生方と福祉課の生徒のご厚意により今年度も安全に退勤できている。 PC環境は昨年度と異なり、勤怠管理システムが導入された。出勤時刻をどこに入力すればよいのか、退勤時刻を打刻する場所がどこにあるのか、音声は全く反応しない。施行当初は入力作業が難航し超過勤務となる日があった。音声の問題は未解決であるが、訓練することで登録できるようになった。 年々ペーパーレス化が進みスクリーンリーダーで読むことができない形式のPDFファイルが増えた。技術を駆使して可能な限り読み取っている。技術の進歩によりできなかったことが少しできるようになる喜びを感じつつ、これからも感謝の気持ちを忘れず明るく元 気に毎日を過ごしたい。 2023年度ノーマライゼーション教育ネットワーク第28回定期総会に参加して埼玉大学教育学部3年 鈴木陽菜 先日は、ノーマライゼーション教育ネットワーク第28回定期総会に参加させていただき、ありがとうございました。教育ネットの活動方針や活動内容について知るとともに、障がいを持つ職員への教育現場の合理的配慮や支援について考える貴重な機会となりました。 定期総会の内容、特にN先生が抱える問題について、次の2点から私の考えを述べさせていただきます。 1つ目は、教育委員会や練馬区の転勤先の校長の、N先生への対応についてです。N先生が受けた言動や今回の問題の経緯を聞き、まずは転勤先の校長の心ない対応に驚きを感じました。N先生のお気持ちを思うと深く心が痛みます。また、教育委員会の対応に関しても、正直なところ不信感を抱いてしまいます。これらの対応が他の地域や社会においてすべて共通するものではないと思いますが、今回のようなことがある以上、変えたり、改善していかなければいけない点は多くあるのではないかと考えます。その中のひとつとして、教育機関での障がいに対する理解のさらなる広まりが必要だと考えます。私自身、教育現場の現状や取り組み、歴史などについて学ぶ中で、障がいを持つ児童生徒への支援や合理的配慮は多く実施されていると感じています。しかし、障がいを持つ教員や職員への支援や合理的配慮についてはこれまで取り上げられたことが少なく、その実施が十分でないと感じます。今回の問題の原因のひとつとしても、障がいに対する理解の低さがあると考えます。また、個人的なイメージとなってしまうかもしれないのですが、教員にはひとりですべてのことを責任を持って行わなければならないというイメージがあると考えます。教員には在籍する児童生徒を守り、教育する責任があることは事実ですが、働き方が多様な形となっている社会の中で、教員同士が協力し合ったり、教育現場と他の機関で連携をとるなどして、働き方がより柔軟になり教員が安心して働くことのできる環境を整え、それが広まることが重要だと考えました。 2つ目は、障がいを持つ職員に対して、まわりの人ができる支援や配慮についてです。今回の内容に、副校長育成支援アドバイザーが視覚障害のサポートをしてくれたことや、授業や採点、事務処理のお手伝いをする補助者が配置されたことがありましたが、私自身そのような配慮がされていることを初めて知りました。今後もひとりひとりの状況に合わせて環境が整えられていくことを願います。それに併せて、身近なまわりの人ができることはないか考えました。私は養護教諭を目指しているのですが、今回のN先生の出来事で養護教諭が出てこないことを少し疑問に思いました。養護教諭は児童生徒だけでなく、職員の健康にも関与します。教育現場において健康を専門にする職として、身体のことや心のことについて相談しやすい存在になったり、共に働き方について考えたり、カウンセラーへつなげるといったことを、私自身できるようになりたいと思いますし、その認識が広まればと思います。 今回の定期総会で、障がいや病気を持つ先生方が抱えるものや教育機関の現状、皆様のお考えを知り、私はまだまだ知らないことがたくさんあるのだと実感し、これから学び考えるとともに、将来教育現場で働く際にはひとりの教員として課題を改善できるよう尽力したいと思いました。 改めまして、定期総会に参加させていただき、考える機会をいただけましたこと、感謝いたします。皆様のご健康とノーマライゼーション教育ネットワークの益々のご発展をお祈り申し上げます。 令和5年8月27日埼玉大学教育学部3年 鈴木陽菜 ノーマライゼーション教育ネットワーク第28回定期総会に参加して令和5年8月27日埼玉大学教育学部3年 奥山紗也佳 育学部で学び、「合理的配慮」という言葉を何度も耳にしてきました。また、以前から宮城先生のお手伝いをさせていただく中で、先生が障害を持たれた後も教員生活を続けられた陰には私たちの先輩である学生のお手伝いがあったとお聞きし、学校という場は障害やその支援に理解があり、障害を持っていても学べる・働ける、そんな場所だと感じていました。しかし、今回の総会にお手伝いとして出席させていただいたことで、学校によって当事者支援の在り方には大きな差があるという現実を知りました。N先生の事件のことをお聞きし、人を育てる職業である教員、そしてその教職員をトップでまとめる立場の人が障害を理解しようとせず差別的な対応をとっているということに大きな衝撃を受けました。 昨今ではノーマライゼーション教育という言葉もよく聞きますが、障害を持つ児童生徒も含めた包括的な教育を行う前に、障害を持つ教職員も適切な支援を受けて働くことができる環境づくりが必要であると強く感じました。一方で岡安先生の勤務されている学校では適切な支援が行われていることをお聞きし、学校もしくは地域によって対応が大きく異なるという現状は私にとって衝撃的なものでした。すべての教職員の安全や権利が守られる学校はどうしたら作っていけるのか自分自身でも考えていきたいと思います。 また、精神保健福祉士の先生による講演を聞くことができたことはとても貴重な経験でした。特に、うつ病がどんな病気かという知識はありましたが、それに対して環境の調整など楽に過ごせる工夫をみんなで考えていくこと、まわりの人は本人のつらさを受け止めながらゆっくり見守ることを理解することができました。学校は精神疾患を抱える児童生徒への配慮だけではなく、教職員の職場としての側面があることを教職員全員が理解・共有し、必要に応じて迅速に環境の整備や見守りをできる制度や雰囲気づくりが必要だと思います。しかし、身体的な障害が理解されずに差別的な対応をされている学校もある現状では、うつ病のような一見目に見えない障害を学校全体で理解しサポートしていくのは簡単なことではないと思います。身体的な障害に対する合理的配慮に加えて、うつ病のような目には見えない障害にも理解しサポートしていく環境を作ることも今後必要であると感じました。 今回、宮城先生のご縁で総会を運営するお手伝いをさせていただき、私自身が将来働きたいと思っている学校現場を経験された皆様の意見を聞くことができました。今後、教育学部で学んだり学校現場に関わったりする時には、今回の定期総会で知った現状や当事者の方の思い、それを受けて挙げられた意見を心に留めて、当事者支援の在り方を考え実行できるよう努めていきたいと思います。この度は貴重な経験をありがとうございました。 |