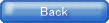
| ノーマライゼーション・教育ネットワーク 会員通信 2023年春号 ~2023年4月5日発行~ 【代表】新井淑則 【事務局】宮城道雄 〔ホームページ〕 URL:http://www.japan-normalizatio.com/ 連絡先〈 郵便 〉〒344-0041 埼玉県春日部市増富763-1 飯島気付 〈 電話 〉090―5994―5131(宮城) 〈メール〉rsj78162@nifty.com(宮城) 会員の皆様、読者の皆様、会員通信2023年春号を発行することになりました。 27回総会以後、教育ネットとして、ホームページの改修をすることになりました。見やすくインパクトのあるホームページにするために,会の紹介の作成しトップページに載せることにしました。現在撮影中ですが、その動画は4月中に出来上がる予定です。ホームページをご覧ください。 また、昨年12月に新会員のN先生(東京都小学校)が入会されました。自己紹介文を掲載します。 ノーマライゼーション教育ネットワーク、略称教育ネットとは 、 私たちは障害を持つ教師が勤務継続をするための、視覚障害や下肢障害などの障害を持つ教師と支援者の市民の会です。学校現場のノーマライゼーションの実現を目指して活動しています。 小学校、中学校高等学校等様々な校種の視覚障害や下肢障害等の障害を持つ教師がいます。障害者になっても創意工夫とパソコンなどの機器の利用と努力で授業や教育活動を継続する方法が確立されています。私たちはそれらを学び障害があっても充実した授業や教育活動ができるように学習し研修活動をしています。 私たちは各当事者との交流を深め協力し合い、障害に応じた働き方を考え、それぞれの物的人的心的な条件を明らかにします。学校や教育委員会にその条件整備を要望し交渉をもって実現します。 2016年に障害者差別解消法と改正雇用促進法が施行されています。行政の責任者や事業主は障害者の働くための条件整備をすること、すなわち合理的配慮の提供が社会に求められています。 私たち教育ネットはこれらの法律の裏付けのもとに、教育現場のノーマライゼーションを実現し障害があってもそれを意識することなく生きられる共に生きる社会を目指して活動しています 教育ネットの活動は、毎月定例会を行い、会員通信を発行しています。また、定期総会を夏に行い講演会を実施してきました。 20周年記念誌を発行しました。 多くの仲間の皆様が会に加入していただき、共に生きる社会の実現に向けて会の活動を拡大して活発にしていきましょう。 ノーマライゼーション教育ネットワーク 連絡先は以下の通りです 代表 新井淑則 事務局 宮城道雄 ?? 344-0041 埼玉県春日部市増富763-1 飯島光治 着付 電話 090-5994-5131 (宮城) メール rsj78162@nifty.com (宮城) 教育ネット紹介の動画脚本 これから教育ネット事務局員に教育ネットとは何かについてインタビューします。 Q ノーマライゼーション教育ネットワークとはどのような会ですか。 A 略称で教育ネットと言います。視覚障害や下肢障害等の障害を持つ教師とその支援者の市民の会です。学校現場のノーマライゼーションの実現を目指して活動しています。 Q ノーマライゼーションとはどのような事ですか。 A 障害があっても無くても共に生きていける社会、障害者が障害を意識しないで生きていける社会を作り上げることです。教育ネットは教育現場のノーマライゼーションの実現を目指して活動している会です。 Q代表はどのような方ですか。 A 視覚障害を持つ新井淑則教諭が代表をしています。埼玉県の皆野中学校で国語科の担当をして担任も務めています。2022年3月退職されました。 Q 病気や事故で障害を持った教師が、教師を続けられますか。 A 教師として授業を行い、教科指導でテストの採点や事務処理を行います。生徒の生活指導など、障害を持ったことによる困難を様々な創意工夫をし、パソコンなどを使ってやることができます。 Q 視覚障害者教師はどうするのですか。 A 視覚障害の場合は、文章を書くために音声ワープロを利用できます。教科書や色々な文章を読むために、朗読ボランティアに読んでもらいます。それをCDにしたものを聞きます。点字を学ぶことも必要です。また、視覚障害の補助者にテストの採点や評価等の事務処理の補助をしてもらったり、また授業では一緒に授業をやり補助をしてもらいます。そのために教育委員会に事務処理や授業の補助のための人的配置をしていただくことが必要になっています。本人の努力と工夫と前向きの姿勢が大切です。 Q 車いす使用の障害を持つ人ではどうですか。 A 段差を解消してスロープの設置が必要です。エレベーターが利用できる環境が必要ですね。 Q 障害者になったとき同じ仲間と連絡が取れればと思いますが。 A 仲間と連絡を取り合い障害を受け入れることが大事なことだと思います。教育ネットは視覚障害者が多かったですが、下肢障害や内部障害、リュウマチ等の教師も存在しました。現在は退職されてしまった方もいますが、それぞれ仲間と知り合い様々な情報交換をすることが大切です。 Q 学校現場では障害者教員を受け入れるのですか。 A 全盲の教師や車いすの教師は実際に働いています。障害者が働くための法律的裏付けとして障害者雇用促進法と障害者差別解消法があります。 Q 障害者雇用促進法とは何ですか。 A 民間企業や行政で障害者が一定の割合で働けるように定めた法律です。民間企業で障害者の雇用率を達成できなかった企業にはペナルティーがあります。行政組織では、障害者活躍推進計画を作成することが義務付けられています。 Q 障害者差別解消法とは何ですか。 A 2016年に施行されました。障害者の個性が尊重され人権が保障されるために、不当な差別を禁止し、合理的配慮の提供が社会に求められています。 Q 合理的配慮とは何ですか。 A 障害者が働くために、企業主や行政の責任者は、障害者が働くための条件整備を行わなければならないことになっています。条件整備、すなわち合理的配慮です。民間企業の場合は、その負担が一定の限度を超えない範囲でと断りがあります。 Q 障害者活躍推進計画とは何ですか。 A 障害者雇用促進法により策定することになっています。 3年から5年間を目途に各行政は作成されることが多いです。 障害者職員の相談活動や、環境整備や研修活動を行う。そのことで障害者職員が働けるようになります。 Q 会としての活動は何をしていますか。 A 月に1回定例会、会員通信の発行、毎年夏に総会の開催、同時に講演会等を実施しています。 また2017年に、20周年記念誌を発行しましたのでお読みください。 Q 障害を持つ当事者に対しては何をしますか。 A 困難を抱える当事者に対しては、会員で話し合いや具体的な対応策を考えます。学校や教育委員会に要望を提出し、それを実現します。 Q 会として特に訴えたいことは何ですか。 A 新しい会員の方が加入してほしいです。障害を持った当事者の方は、勿論です。同時に、インターネット等のIT技術を使いこなせる方が是非入会していただければと考えています。 以上でインタビューを終わります。 「よしのり先生、最後の授業」の感想 飯島光治 2023年1月19日、NHKの30分番組で、再放送です。感動しました。 番組から 1.新井さんが、野球部とおもう生徒にノックをしている所。玉を受け取り、新井さんが球を上げ、バットで。 お見事です。 2.授業中、生徒一人一人に声をかけていく。ティームティーチングなのでできるのですが 新井さんだけでは。 3.3年生のクラスで「一番良い所、一番悪い所」で今までの教師生活の中で、一番悪い所は、成績が悪いこと。一番良い所は、一年生の時入学するとき、お母さんと相談したことがあった。皆はその生徒を温かく迎えてくれた。その時みんなを3年間見るぞと思ったとありました。 以上の言葉は、長く残るのではと思いました。 番組で宮城さんのことが出てきます。「宮城先生から新井さんも授業できるよの言葉があるから現在の自分がある。」とありました。宮城さんから私が話を聞くと言葉だけでなく、実際各地の授業見学をしています。 またティームティーチングの龍口先生。長瀞中学校時代の落合先生は、新井さんが皆の中学校に移ってからも支援に来てくれた。お二人ともテレビに出てきました。 新井さんの言葉として教師と生徒は、「上下関係に」あるが、私の場合は生徒に協力してもらい、「上下関係」だけではない。そこに特徴がある。とありました。 新井さんは、日々の仕事をしながら、今まで毎年の公開授業、多くの講演、また本も書かれています。本当にご苦労様でした。私は講演を聞いていますが、はっきりした分かりやすい言葉でした。 所で今までの新井さんのテレビで、教育ネットの事が紹介されていません。新井さんの中学校復帰では、長い間県教育委員会との交渉がありました。新井さんは教育ネットの代表として、月1回の定例会には、秩父から参加しています。 尚、今回会員通信(2022年12月8日発行)にお知らせした2 の放送日が変更と連絡がありました。会員の方からそのことでお電話がありました。 こういうことがあるんだと。 (2023年2月記) |